令和7年7月28日、31日の二日間、箕輪中部小学校の唐木先生が異業種研修のため来館されました。教員として10年目を迎えた学校の先生が、異なる業種の体験をすることで、より視野を広め、豊かな人間性をやしなうことを目指して行われています。 二日間の体験で学んだこと、感じたことを唐木先生にまとめていただいたので、ブログでご紹介します。
「地域の材を受け継ぐ」
今回、教員の異業種研修として学芸員さんのお仕事を体験させていただきました。子どもたちと共にお蚕様と生活している私にとって、より養蚕や製糸業について学ぶことができるまたとない機会になりました。
さて、みなさんは今お住いの地域の歴史・文化・伝統産業・伝統農業などをご存知でしょうか。(以下、地域の材と呼ばせていただきます。)それらは、地域を司ってきたものであったり、人々の暮らしを支えてきたものであったりすると思います。そして、ここ岡谷市を代表する地域の材は、製糸業です。
2日間の間に、岡谷市史編さんプロジェクトチームの会議にも参加させていただきました。その中で、レイクウォーク前の蚕糸公園がなぜ三角形の形をしているのか、岡谷駅がなぜ今の場所に建設されたのかなどのお話を伺いました。いずれも、繭や生糸の物流を考えてのことだそうです。天竜川沿いを通ると、「船着場跡」という看板をよく見かけます。産業が町づくりにも大きく影響したのですね。私の祖母は諏訪市に暮らしていますが、昔養蚕をしていたと話してくれました。今勤めている上伊那郡でも養蚕が盛んでした。養蚕業が衰退したあと、諏訪郡や上伊那郡では精密機械工業が発展していきました。これだけとっても、製糸業が今の暮らしにどれだけの影響を及ぼしているかが分かります。
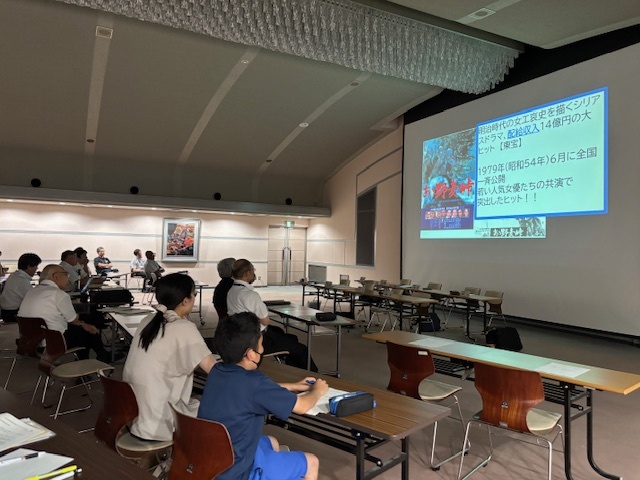

今回、学芸員さんの仕事を間近で見たり一緒に仕事をしたりさせていただいて一番感じたことは、学芸員さんは地域の材を受け継いで伝えていくスペシャリストだということです。歴史的にも価値がある展示物や収蔵品の管理・保管、そこにある人々の歴史・文化・思いを受け止め次の世代へと伝えていく。なによりも、岡谷の製糸業や養蚕、お蚕様に敬意をもって接する姿。その結晶が岡谷蚕糸博物館から感じることができます。

私も教員として地域に愛着をもった子どもたちを育成していきたいと考えています。学芸員さんくらい地域の材を追求し、それを子どもたちと共に学んでいく教員でありたいと改めて感じました。私たち教員は、「その地域を知りたかったら地域をめぐれ」とよく言われます。岡谷を知りたかったら、岡谷蚕糸博物館へ足をのばせば岡谷の方々の歴史や思いにふれることができます。みなさんも岡谷蚕糸博物館へ、どうぞお越しください。なによりも、お蚕様がとてもかわいいですよ!
